TOEICで高得点を取るためには高い英単語力が必要ですが、単語の勉強ってとにかく地味なので、やる気が続かないこと多くないですか?
私も、TOEIC900点を目指していた当時は単語の勉強が1番嫌いだったのですが、リーディングのスコアを上げるべく、色々工夫をしながら頑張っていました。
今回は、そんな私が「これはいい!」と思った英単語勉強法についてご紹介したいと思います。
やる気を保つには勉強方法に工夫が必要
英語の勉強は総じて「継続」が大切ですが、英単語の勉強はやる気を保つことが難しく継続しづらい取り組みだと思います。
単語の勉強にやる気が維持できない主な原因は以下の通りです。
- 地味過ぎる
- 成果が見えづらい
- 区切りを付けづらい(ダレてしまう)
逆に言えば、上記原因を解消できれば、無理なく単語勉強を継続することができる訳です。
というわけで、私が自ら考案・実践し、一定の成果をあげることができたおすすめの単語勉強法について、以下よりまとめていきたいと思います!
「単語100問テスト」のすすめ
おすすめの単語勉強法とは「単語100問テスト」です。
具体的には、憶えたい英単語100問を1枚のテストとしてまとめ繰り返し解く勉強方法です。
文字だけだとイメージしづらいかと思いましたので、実際に私が作った単語100問テストをご紹介。

単語100問テストの特徴
単語100問テストには以下の特徴があります。これは、先程挙げた「英単語勉強のやる気が維持できない」原因を解消するものとなっています。
単語100問テストの特徴
- テスト形式なので視覚的にやる気が出る
- テスト形式なので正答数が明確で成果が見えやすい
- テスト形式なので勉強の区切りが付けやすい
単語100問テストの作り方、実施方法
さて、前段が長くなりましたが、いよいよ単語100問テストの作り方、テストの実施方法をご紹介したいと思います。
※プリンターが必要になります。
ステップ1:単語100問テストを作成する
まず、憶えたい英単語を100個集めエクセルに一覧化します。
エクセルシートのレイアウトは、憶えたい単語が書かれた「英単語欄」と、回答を書くための「回答欄」があればどのような形でもOKです。
私の場合「金のフレーズ(TOEIC学習者の王道参考書)」の中から憶えたい英単語を100個ピックアップしました。
ステップ2:解答シートを作成する
単語100問テストが完成したら、答え合わせの際に使う解答用シートを作ります。要は回答欄に答えが書かれたシートです。
具体的には、単語100問テストのシートをコピーして、解答欄に「答え(=その英単語の意味)」を書き込んでいく感じです。
これは毎回の答え合わせをスピーディーにするための工夫です。解答シートがあれば、テスト終了後に横に並べて比較することで、答え合わせがスムーズになります。
ステップ3:テストを実施する
作った単語100問テストをプリントアウトし実際にやってみます。
制限時間は10分程度にして、分からない単語は考えずに飛ばします。
最初は分からない単語だらけだと思いますが、躊躇せずに飛ばします。すぐ思い出せない=身に付いていないということなので、その段階では深追いしても時間の無駄なのです。
ステップ4:答え合わせをする
テストが終わったら、解答用シートを横に並べて答え合わせし、正答数を出します。
100問中何問正解できたかを明らかにすることは結構大切で、今後繰り返しテストを行っていく中で成長のバロメータとなりますし、勉強のモチベーションになります。
おそらく最初は半分に満たない正答数になるかと思いますが、それが普通なのでお気になさらず。
ステップ5:満点になるまで繰り返しやる
答え合わせをした直後に、もう1回同じテストを実施します。ここが1番大切なステップです。
繰り返し実施することで、間違った単語も正答した単語も記憶に定着させることができます。特に、間違えた単語は何度も触れないと記憶に定着しづらいので、繰り返し学習する(思い出す)必要があります。
できれば、満点が取れるまで繰り返し解いた方が良いのですが、あまり繰り返すと時間がかかり過ぎるので、満点が取れない場合は一定回数で切り上げ、次回に持ち越しましょう。
ステップ6:日を置いて繰り返しやる
ステップ3~5までが「1回分の勉強メニュー」となります。この勉強メニューを日を置いて繰り返すことで、記憶へのよりいっそうの定着が期待できます。
どのような頻度で実施すべきかですが、結論から言うと「忘却曲線」を参考にスケジューリングします。忘却曲線とは人が何かを憶えた際の経過日数ごとの忘れ具合を示した曲線です。
これを逆手に取ると、復習するのにベストなタイミングが分かります。そのタイミングで単語100問テストを再実施するわけです。
諸説あるので細かい説明は省きますが、復習する(再テストする)タイミングは以下が良いでしょう。
・翌日
・1週間後
・2週間後
・1ヶ月後
タイミングはそこまで厳密じゃなくても大丈夫です。あくまで目安として考えてください。
私の「単語100問テスト」実施結果
単語100問テストの内容は人それぞれですが、参考までに、私のテスト結果(正答数)をお見せしたいと思います。
以下の表は、マイ単語100問テストの正答数を記録したものです。表が2つありますが、単語100問テストを2種類作っていたからです(計200個の単語を憶えようとしてました)。
※赤文字には特に意味はないのでお気になさらず。笑

各実施日で最大3回同じテストを行っていますが、日を追う毎に1回目実施時の正答数が多くなっていることが分かります。
また、同じ実施日でも、2回目、3回目実施時の方が点数が高くなっていることが分かります。
単語100問テストを継続実施してみた感想
感想ですが、まず、テスト特有の緊張感があるため、学習がマンネリ化しづらかったように感じます。
また、正答数が明確に出るので、点数が高かった際も低かった際も、次回に向けたモチベーションが上がりました。点数を毎回表にまとめていたことも、自身の成長が実感でき、モチベーションアップに繋がったと思ってます。
さらに、テスト形式ゆえに、勉強の開始・終了が明確で勉強時間が一定化でき、日々の勉強に取り入れやすかったです。勉強の開始・終了が不明確、勉強時間が不明確だと、スケジューリングしづらいですからね。。
まとめると、単語100問テストのおかげで、単語勉強を無理なく継続できました!
勉強は、継続できる工夫を
以上が私の提案する英単語学習メソッド「単語100問テスト」ですが、皆さんも勉強を継続させるための工夫は常日頃から考えてみてください!
スコアアップ≒継続力アップだと思うので!
現場からは以上です。
おすすめの記事
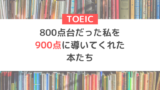
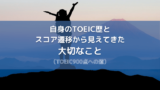

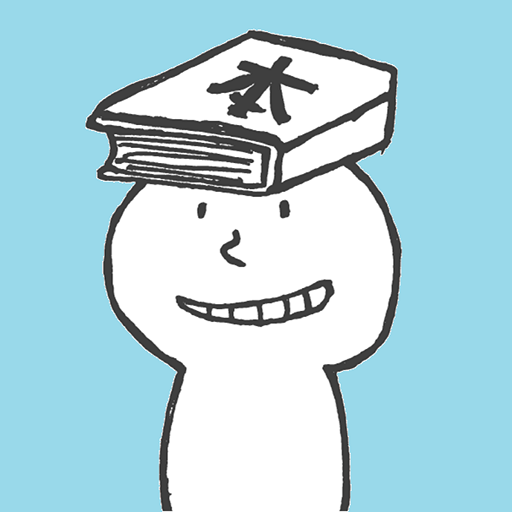
コメント