学生期間の年金保険料納付を猶予してもらえる「学生納付特例」ですが、ある日突然「追納」の案内が来たります。
そもそも追納すべきなのか?追納するメリットは?しないデメリットは?と色々知りたくなってしまうトピックスだと思うので、追納経験者として一部始終をまとめたいと思います!
この記事の主な読者像
- 今会社員で、
- 学生時代に学生納付特例により年金の保険料を支払っていない方
私の「追納」体験談
まずは参考までに、私の追納体験談をまとめます。
発端は年金事務所からのハガキ
私が国民年金保険料を追納するきっかけとなったのは、年金事務所からの1枚のハガキでした。

年金事務所からのハガキ。なんじゃこれ!という感じでした
ハガキのタイトルは「国民年金保険料追納のご案内」。
正直何のことか分からなかったので、
そうだ、無視しよう!
と一瞬考えたのですが、放っておくとよろしくない感じがしたので、ちゃんと向き合ってみることにしました。
国民年金保険料の追納とは?
さて、そもそも国民年金保険料の追納って何だよという話ですが、文字通り、国民年金保険料の不足分を後から納めるということです。
この段階でまず思うことは「不足分って何だ?」ということ。というのも、私のような会社員は、毎月の給料から厚生年金保険料+国民年金保険料が自動的に支払われているため、支払いが不足するという事態にはならないはずなのです。
え、会社からの支払い漏れ?
と思ったりもしましたが、違いました。結論から言うと、追納の対象となっていたのは学生時代に支払えなかった国民年金保険料のことでした。
追納対象は「学生時代の未納分」
本来、国民年金の保険料の支払い義務は20歳から発生します。ただし学生については特に定期収入があるわけではないので、国民年金保険料の支払いを猶予してもらうことができます。
それが「学生納付特例制度」です。
おそらく、大学、大学院進学をされた方はほぼ全員がこの制度を利用していたのではないでしょうか。
今回私が追納することになったのは、まさに学生納付特例を利用した期間に未納となっていた保険料でした。
追納しない場合のデメリット
ここまで読んでくださった方の中には「私も学生納付特例を利用してたけど、追納しないといけないの!?」と思った方もいらっしゃるかと思います。
結論から言うと、学生納付特例による未納分に対する追納は必須ではありません。
追納しなくても罰則とかそういったものはないです。ただ、追納をしないことによるデメリットはあります。
詳しくは次のとおりです。
将来もらえる年金が減る
追納しない場合の大きなデメリットは、将来もらえる年金が減ってしまうという点です。2023年1月現在、年金(老齢基礎年金)の受給開始年齢は65歳からとなっていますが、そこからもらえる年金が減ってしまうのです。
というのも、学生納付特例では、保険料の支払いは猶予されますが、学生納付特例を適用した期間は保険料を支払っていない扱いになるからです。
当然と言えば当然なのですが、要は「保険料支払っていないんだから、受給できる年金も減らしますね」ということです。
将来もらえる年金はどのくらい減るのか
では、学生納付特例を利用し、かつ国民年金保険料の追納を行わなかった場合、将来もらえる年金はどの程度減ってしまうのでしょうか。
細かい計算は省きますが、例えば学生納付特例で1年間分の国民年金保険料納付を猶予し、その後追納しなかった場合、もらえる年金は年額2万円ほど減ります。
「なんだたったの2万か」と思った方は要注意です。というのも、公的年金は生きている限りずっともらえるものなので、たとえ年に2万円でも、例えば65歳から90歳まで25年間生きた場合、2万×25年=50万ほど損をしてしまうわけです。
け、結構損だっ!
そして、1年間だけ学生納付特例を受けたという方はほぼいないと思います。20歳以上の学生期間を考えると、猶予期間が2年以上の方がほとんどではないでしょうか。
猶予期間が2年間の場合、もらえる年金は約4万円減ります。90歳まで生きた場合、約100万円損をする計算です。ざっくりですが、先ほどの倍ですね。
※最終的な損得を考えるうえでは、追納する保険料の総額も加味する必要があります。
追納する場合のメリット
学生納付特例期間分の国民年金保険料を追納するメリットは、大きく2つあります。
1つは、先ほどのデメリットの裏返しで、将来もらえる年金が減らないという点です。
そしてもう1つのメリットは、節税ができるという点です。
追納することで節税ができる
節税?と聞いてもピンと来ない方もいるかと思いますが、国民年金保険の追納を行うことで、所得税と住民税が減ります。
というのも、所得税と住民税を算出する元となる所得額から追納した額を差し引く(控除する)ことができるからです。
控除の枠としては「社会保険料控除」という枠となりますが、詳しく書くとややこしいので割愛します。
所得税・住民税はどのくらい減るのか
じゃあ所得税と住民税はどのくらい減るのか、という点ですが、ものすごくざっくりいうと、例えば所得税+住民税の税率が合計20%の場合は、追納した金額の20%を節税できることになります。
通常、国民年金の追納額は数年分の国民年金保険料の蓄積となるので、額もそれなりになります。その20%が節税できる(要は自由に使えるお金が増える)のですから、お得感がすごいですね!
年金保険料「追納」のやり方
さて、ここまで読まれた方は、追納した方が良いじゃん!という考えになっているかと思いますが、追納のやり方について、私の経験ベースでまとめたいと思います。
まず、全体感をつかんでもらうために、流れを箇条書きにします。
追納の流れ
- 最寄りの年金事務所で納付書をもらう
- 納付書を用いて支払いを行う
- 年末調整時に申告する
それでは順を追って説明していきます。
最寄りの年金事務所で納付書をもらう
まずは最寄りの年金事務所に行き、国民年金保険料の追納を行いたい旨を伝え、手続きを行います。手続きが完了すると、支払いに必要な納付書がもらえます。
所要時間について、待ち時間はその場所によるかと思うので割愛しますが、手続き自体は30分程度で完了しました。
手続きの際に必要となる物は特にないのですが、基礎年金番号を聞かれるので、年金事務所からのハガキや年金手帳を持っていくことをおすすめします。基礎年金番号を憶えている人の方がレアだと思いますので。。
納付書を用いて支払いを行う
年金事務所でもらった納付書で支払いを行います。コンビニエンスストアや郵便局、銀行等で支払いができます。
近場にあるという意味ではコンビニのほうが便利なのですが、私は郵便局や銀行をおすすめします。というのも、納付書は1枚ではなく、学生納付特例を利用した期間に応じて数が多くなり、支払いに時間がかかるからです。
例えば私の場合は約3年分の納付書をもらいましたが、数にして8枚ありました。多っ!
人の往来が激しいコンビニのレジで、これらを1枚ずつ支払っていく勇気は私にはなかったので、コンビニよりは人の往来が少ない郵便局で支払いを行いました。
また、追納の支払いは原則現金払いとなるので、手持ちがない場合は予め相当額を引き出しておく等の準備が必要です。
私は郵便局で支払いをしたので、ゆうちょ銀行の口座から直接振り替えてもらえました。支払い手続きの時間は、振替の手続きも含めて20分程度でした。
年末調整時に申告する
納付書での支払いが完了した段階で、将来もらう年金が増えること(減らないこと)が確定します。ただし、節税できるというメリットを享受するためにはまだやることがあります。
それは、年末調整時の申告です。具体的に言うと、支払った追納額を社会保険料控除として申告する必要があります。
確定申告でも同じことができますが、会社員の場合は年末調整の方が格段に楽なので、これを利用しない手はないです。というわけで、年末調整の申告時期(だいたい11月頃ですかね)には、会社に忘れずに申告しましょう。
年末調整の申告の際に必要となるものは、納付書での支払いを行った際に返ってくる領収証書です。なくさない限りは手元にあるはずなので、その原本を会社に提出すればOKです。
ここまで完了すれば、将来もらう年金についても、節税についても完璧です!
追納は、面倒だけどやった方がいい
以上、学生特例期間の国民年金保険の追納方法についてまとめてみました。
追納する/しないは個人の自由ですが、私的には、追納はした方がいいと思っています。
手続きが少々面倒ではありますが、それによって得られる将来の安心と直近のお得さ(税金の控除)が結構なメリットに感じられるからです。
というわけで、皆さんも是非追納を!(何らかの回し者ではないです。笑)
現場からは以上です。
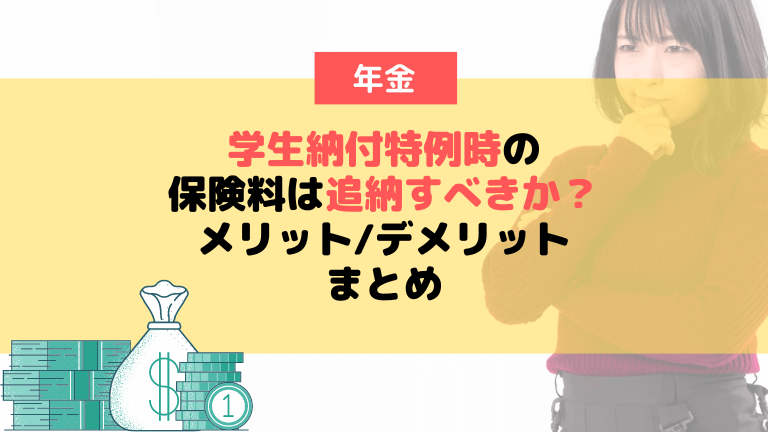
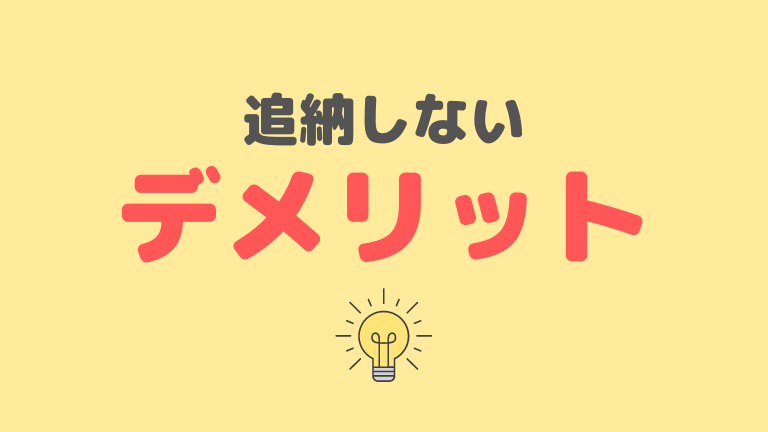
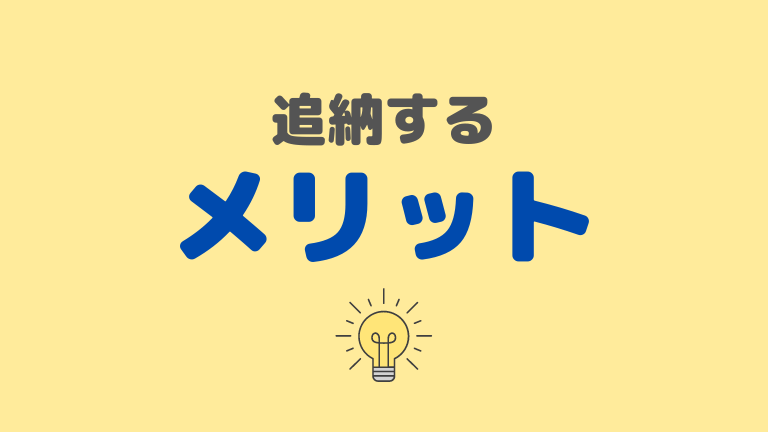
コメント